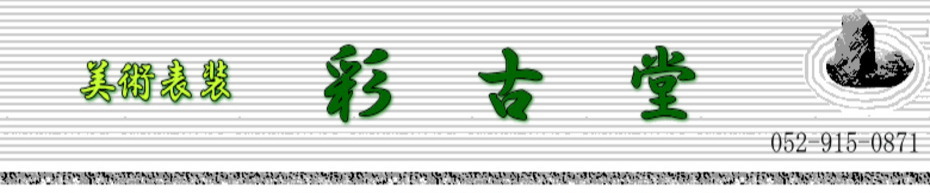① どうようなものが表装にできますか?
書道家が画仙紙(和紙)を半分に切ったサイズに書かれた作品。 住職が書かれた名号、法名軸、曼荼羅の大幅軸。 絵絹・和紙に書かれた仏画、日本画。
四国八十八ヶ所・西国三十三ヶ所等の朱印軸、集印軸、納経軸。佛表具・仏表具・御影額。 歌舞伎の隈どり、拓本、魚拓など。 団扇、扇子などの扇面の本紙。
古物表具など折れや破れのひどい物でも大丈夫です。
② いくらぐらいで表装して頂けますか?
お客様のご予算に合わせて表装させていただきます。表装の裂地は大変種類が多く、値段もさまざ まです。古物表具の場合、はがし代、修理修復代、洗い・しみ抜き代、傷み具合によって値段が変わります。表具師が提案させていただきますので、お気軽にご相談ください。
③ 期間はどのくらいかかりますか?
ご依頼の内容により変わりますが、目安として表装のみであれば2ヶ月、本紙の洗い・しみ抜き、古書画の修理修復、掛け軸の修理等は3ヶ月ほどみてください。額・屏風・衝立は3ヶ月程度かかります。
④ 掛軸の取扱いの注意点と保存方法?
掛け軸はある程度高温多湿に適応できるように作られていますが、過度の『湿気』や『乾燥』を嫌います。 掛け軸は表具裂を和紙で裏打ちされているので乾燥には大変弱く暖房を点けた部屋に掛け続けていると軸
が反ってしまいます。暖房の効いた部屋で反りを防ぐためには加湿器を点けて湿度が50~60度になるように してください。直射日光や急激な温度変化のある場所には軸を掛けないようにしてください。掛け軸を箱に収めるときは天気の良い日に、手の汗や汚れを拭い軸のほこりをはたきで落してから桐箱に
収納していただくと『カビ』や『染み』や『ホシ』が予防できます。雨の日に湿気を含んだまましまうとカビが生え たり、『肌裏』・『増裏』・『総裏』が浮く原因になります。虫干しは春と秋の年二回、掛け軸に風を通すことで本紙の湿気が取り除くことができれば『カビ』や『染み』
を防ぎ掛け軸を長持ちさせることが出来ます。長い間掛けっ放しにしておくと『焼け』や『染み』が出てくるので 注意が必要です。
⑤ 竹屋町裂?
紗地に平金糸で文様を縫いつけた裂地。元和年間(1615-24)に堺に訪れた明の工人からこの技法を学んだ 銭屋、松屋の両人が、京都の竹屋町でこの織物を織り始めたことから、竹屋町裂と呼ばれるようになった。表装に用いる金紗の一つ。
⑥ 経師(きょうじ)と表具師のちがい?
経師と表具師は同じ職業です。経文などを多く扱っていたため、経師と呼ばれるようになり、東京(関東)地方では今でも経師といいます。
⑦ 茶掛・茶掛表具・茶掛表装?
お茶席で掛けられる掛物。「茶掛=輪補表具」ではなく、幢補表具であってもお茶席で掛けられる掛物の全般を「(お)茶掛」という。宗匠・茶人の書や絵、画讃や禅僧の墨蹟などが多い。お茶席にふさわしい趣の取り合わせの表具(表装)・掛物。