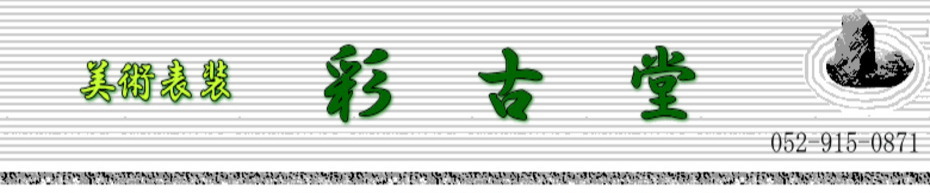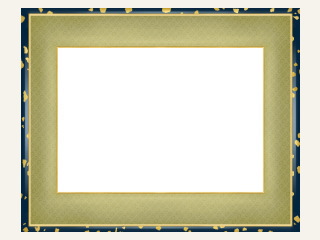書や絵画に裂(きれ)地を様式に合わせて継ぎ合わせた巻物で、床の間や壁面などに掛けて空間の飾りとしたり、鑑賞できるように仕立てたもの。 神仏の画像を礼拝するためのものとして発祥し、飛鳥時代の仏画を表装したものが、日本最初の掛軸とされています。
鎌倉時代の禅宗文化の影響、室町時代での床の間の出現、茶の湯の流行などによって仏画だけでなく広く一般絵画ほか墨筆・古筆切・懐紙などを掛軸にして鑑賞するようになりました。
形式は大きく表補(真)・幢補(行)・輪補(草)の三形式があり、さらに真の真・真の行・真の草・行の真・行の行・行の草・草の行・草の草、このように八種に分かれる。
茶道では、千利休によって最も重要な道具とされ、墨蹟のものがその筆頭となった。近代も日本画の鑑賞・保存に大きな役割を果たし、今日に至っている。